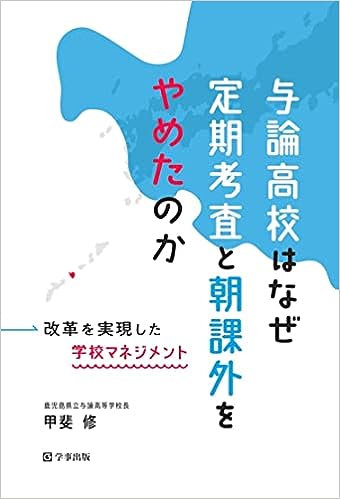与論高校はなぜ定期考査と朝課外をやめたのか
改革を実現した学校マネジメント
鹿児島県の離島・与論島の唯一の高校が定期考査と朝課外を廃止した。なぜ普通の全日制普通科高校でこのような改革が実現できたのか。どこから手を付け、どう変えていったのか。与論高校の学校マネジメントの全貌をまとめた。
鹿児島県の離島・与論島の唯一の高校が定期考査と朝課外を廃止した。なぜ普通の全日制普通科高校でこのような改革が実現できたのか。 どこから手を付け、どう変えていったのか。与論高校の学校マネジメントの全貌をまとめる。
目 次
はじめに
第1章 あなたの高校は未来を見据えているか
1 離島の小規模高校ができること
地域にとっての高校の存在意義
高校の特色化・魅力化
2 新学習指導要領と観点別評価
資質・能力の三つの柱
観点別評価と「指導と評価の一体化」
3 知りながら害をなすな
二つの学習評価
「序列付け」は過去のもの
大きく方向転換した学習評価の在り方
マネジメントを司る校長の責任
4 組織のマインドセットをどうするか
新学習指導要領と高大接続改革
新学習指導要領を理解する
教職員のマインドセット
5 WHY(なぜ)から始める
ゴールデン・サークル理論
まず校長がWHYを語る
コラム 校長講話1 「予測困難な時代に自分のキャリアを切り拓いていくために」
第2章 学習指導と学習評価の在り方を見直す
1 授業と学習評価の現実
定期考査を軸とした学習評価
評価とは本来「観点別」である
2 なぜ定期考査は不要なのか
定期考査ではできないこと
単元や題材のまとまりごとに評価するメリット
単元や題材のまとまりごとに評価するデメリット
観点別評価を前倒しで実践する
まずは問題提起から
3 単元ごとの評価に移行するために何が必要か
自校の「単元シラバス」を定義する
シラバスの意味
シラバスをつくる意義
4 〝学びの地図〟を生徒に手渡す
校訓と資質・能力の三つの柱
二つの地図を合わせ見る
シラバスで変わり始める授業
コラム 校長講話2 「自分の足下を掘れ そこに泉がある」
第3章 学校に創造的な時間を取り戻す
1 朝課外の〝功罪〟
朝課外と個別最適な学び
保護者の要請と地域の期待
過去ではなく未来を選ぶ
改革は一気呵成に進める
2 何が生徒の主体的な学びを妨げるのか
教職員の頭の中の授業計画
生徒の限られた時間と宿題
3 教職員の声にどう対応するか
次年度方針を決める
教職員の声に応える
WHYから始め、HOWとWHATへ
外部等への説明
4 試行から見えてきた成果と課題
実践開始当初の試行錯誤
1学期の実践の課題
ドリル教材の単元テストでの取扱い
ルーブリックに対する共通理解
3年生の入試問題演習をどうするか
学校評価で感じた手応え
1年間の実践から言えること
5 業務改善は「エッセンシャル思考」と「関係の質」が鍵
より少なく、しかしより良く
成功循環モデル
学ぶ機会と雰囲気をつくる
コラム 校長講話3 「今いる場所でベストを尽くす」
第4章 自校のビジョンを明確にする
1 ビジョンがつくるこれからの高校
2 地域のよりよい未来づくりに貢献する
小学校のアシスタント・ティーチャー
島のしごとフェア
探究活動
図書室の一般開放
3 「使う言葉」が組織の文化をつくる
校長の覚悟を示す
言葉が世界をつくる
コラム 校長講話4 言葉が世界をつくる
第5章 これからの学校経営を考える
1 校長は自校のカリキュラム・マネジメントを語れるか
自校のWHYは何か
セロリ・テスト
自校は何を目指すのか
2 自校の「弾み車」は何か
弾み車の法則
独自の「弾み車」をつくる
3 より重要になる戦略的広報活動
「広報」とは何か
なぜ与論高校の取組が記事になったのか
ニュース価値の3要素
選ばれる学校になるために
4 リーダーとしての学校管理職の役割
まず校長が「学びのリーダー」になる
管理職の三つの職能
マルチステージの人生、高校がやるべきこと
コラム 校長講話5 「これからの時代に求められるリーダーシップとは」
おわりに
目 次
はじめに
第1章 あなたの高校は未来を見据えているか
1 離島の小規模高校ができること
地域にとっての高校の存在意義
高校の特色化・魅力化
2 新学習指導要領と観点別評価
資質・能力の三つの柱
観点別評価と「指導と評価の一体化」
3 知りながら害をなすな
二つの学習評価
「序列付け」は過去のもの
大きく方向転換した学習評価の在り方
マネジメントを司る校長の責任
4 組織のマインドセットをどうするか
新学習指導要領と高大接続改革
新学習指導要領を理解する
教職員のマインドセット
5 WHY(なぜ)から始める
ゴールデン・サークル理論
まず校長がWHYを語る
コラム 校長講話1 「予測困難な時代に自分のキャリアを切り拓いていくために」
第2章 学習指導と学習評価の在り方を見直す
1 授業と学習評価の現実
定期考査を軸とした学習評価
評価とは本来「観点別」である
2 なぜ定期考査は不要なのか
定期考査ではできないこと
単元や題材のまとまりごとに評価するメリット
単元や題材のまとまりごとに評価するデメリット
観点別評価を前倒しで実践する
まずは問題提起から
3 単元ごとの評価に移行するために何が必要か
自校の「単元シラバス」を定義する
シラバスの意味
シラバスをつくる意義
4 〝学びの地図〟を生徒に手渡す
校訓と資質・能力の三つの柱
二つの地図を合わせ見る
シラバスで変わり始める授業
コラム 校長講話2 「自分の足下を掘れ そこに泉がある」
第3章 学校に創造的な時間を取り戻す
1 朝課外の〝功罪〟
朝課外と個別最適な学び
保護者の要請と地域の期待
過去ではなく未来を選ぶ
改革は一気呵成に進める
2 何が生徒の主体的な学びを妨げるのか
教職員の頭の中の授業計画
生徒の限られた時間と宿題
3 教職員の声にどう対応するか
次年度方針を決める
教職員の声に応える
WHYから始め、HOWとWHATへ
外部等への説明
4 試行から見えてきた成果と課題
実践開始当初の試行錯誤
1学期の実践の課題
ドリル教材の単元テストでの取扱い
ルーブリックに対する共通理解
3年生の入試問題演習をどうするか
学校評価で感じた手応え
1年間の実践から言えること
5 業務改善は「エッセンシャル思考」と「関係の質」が鍵
より少なく、しかしより良く
成功循環モデル
学ぶ機会と雰囲気をつくる
コラム 校長講話3 「今いる場所でベストを尽くす」
第4章 自校のビジョンを明確にする
1 ビジョンがつくるこれからの高校
2 地域のよりよい未来づくりに貢献する
小学校のアシスタント・ティーチャー
島のしごとフェア
探究活動
図書室の一般開放
3 「使う言葉」が組織の文化をつくる
校長の覚悟を示す
言葉が世界をつくる
コラム 校長講話4 言葉が世界をつくる
第5章 これからの学校経営を考える
1 校長は自校のカリキュラム・マネジメントを語れるか
自校のWHYは何か
セロリ・テスト
自校は何を目指すのか
2 自校の「弾み車」は何か
弾み車の法則
独自の「弾み車」をつくる
3 より重要になる戦略的広報活動
「広報」とは何か
なぜ与論高校の取組が記事になったのか
ニュース価値の3要素
選ばれる学校になるために
4 リーダーとしての学校管理職の役割
まず校長が「学びのリーダー」になる
管理職の三つの職能
マルチステージの人生、高校がやるべきこと
コラム 校長講話5 「これからの時代に求められるリーダーシップとは」
おわりに
学事出版オンライン
ストアで購入
ストアで購入
ネット書店で購入