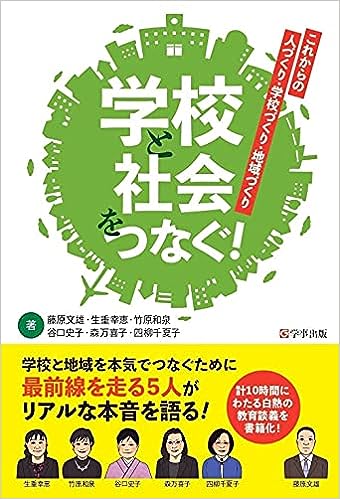学校と社会をつなぐ!
これからの人づくり・学校づくり・地域づくり
学校と社会をつなぐプロたちが、学校・地域社会の連携・協働の当事者として直面した課題、その乗り越え方、これからの教育のために何が必要なのかを伝える。
本書では、5人の女性たちが学校と社会をいかにつなげるかというテーマで論じ合います。
「学校と社会をつなぐ」当事者として直面してきた課題やご自身の成 長、そして姿勢を記述した。
学校と社会が本気でつながるために、今、何が必要 か。学校現場でも参考になる話題も豊富に掲載。
目 次
プロローグ
学校と社会をつなぐ「チェンジメーカー」たち
「学校と社会つなぐ」政策の背景
「連携・協働答申」が捉えた「背景」
「連携・協働答申」の打ち出した「ビジョン」
「連携・協働答申」の打ち出した「処方箋」
5人の「チェンジメーカー」紹介
PART 1 学校・地域社会の連携・協働はなぜ必要か
連携・協働における「現在地」を整理する
連携・協働はなぜ必要か1 学校の役割の肥大化
連携・協働はなぜ必要か2 子どもに社会を「生きる力」を養う
現状の課題1 学校・地域間にある意識的な壁をどう乗り越えるか
現状の課題2 新しい取り組みに対する教員の抵抗感をどう取り除くか
現状の課題3 連携・協働をどのような形で進めるか
現状の課題4「 地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」をどう進めるか
取り組みをきちんと「価値付け」することが重要
PART 2 連携・協働の視点1 キャリア教育 -学校・地域それぞれの役割-
「職場体験=キャリア教育」という大いなる誤解
学校の全ての時間がキャリア教育につながっている
何のためにやるのか、「上位目的」を確認する
キャリア教育を推進する上でのポイント
キャリア教育は「生き方教育」
PART 3 連携・協働の視点2 場づくり -会議にはない可能性-
東山田中学校コミュニティハウス設立の経緯
「箱」ができた後は、「魂」を入れることが大切
評価から離れた「場」の重要性
カリキュラムづくりにも地域が関わる時代
人が集まり、情報が行き交うプラットホーム
PART 4 連携・協働の視点3 防災 -学校と地域をつなぐツール-
3千人近くが集う学校・地域合同の防災訓練
防災訓練を通じて、学校・地域の相互理解が深まる
「防災訓練」は、訓練のためだけにやるのではない
「防災」を基点に、学校・家庭・地域の役割を見直す
コロナ禍で見えてきた学校の課題
非常時こそ、学校は地域を頼るべき
コロナ禍におけるポジティブな変化
学校運営協議会をスクラップ装置に
PART 5 連携・協働の視点4 マネジメント -地域と学校をつなぎ成果を出すために-
「地域とともにある学校づくり」には、経営資源が必要
「経営者」としての校長をどう育成し、支援するか
教職員が、主体的・自律的に動くための組織づくり
子どもたちを自律させるための「主権者教育」
PART 6 提言とまとめ-私たちはこれからも歩み続ける-
「誰一人取り残さない」教育を目指す
子どもを「信じる」社会総がかりの教育
私たちはこれからも歩み続ける ―今後取り組んでいきたいこと―
エピローグ これからも共にしなやかに切り拓いていく
「学校と社会をつなぐ」当事者として直面してきた課題やご自身の成 長、そして姿勢を記述した。
学校と社会が本気でつながるために、今、何が必要 か。学校現場でも参考になる話題も豊富に掲載。
目 次
プロローグ
学校と社会をつなぐ「チェンジメーカー」たち
「学校と社会つなぐ」政策の背景
「連携・協働答申」が捉えた「背景」
「連携・協働答申」の打ち出した「ビジョン」
「連携・協働答申」の打ち出した「処方箋」
5人の「チェンジメーカー」紹介
PART 1 学校・地域社会の連携・協働はなぜ必要か
連携・協働における「現在地」を整理する
連携・協働はなぜ必要か1 学校の役割の肥大化
連携・協働はなぜ必要か2 子どもに社会を「生きる力」を養う
現状の課題1 学校・地域間にある意識的な壁をどう乗り越えるか
現状の課題2 新しい取り組みに対する教員の抵抗感をどう取り除くか
現状の課題3 連携・協働をどのような形で進めるか
現状の課題4「 地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」をどう進めるか
取り組みをきちんと「価値付け」することが重要
PART 2 連携・協働の視点1 キャリア教育 -学校・地域それぞれの役割-
「職場体験=キャリア教育」という大いなる誤解
学校の全ての時間がキャリア教育につながっている
何のためにやるのか、「上位目的」を確認する
キャリア教育を推進する上でのポイント
キャリア教育は「生き方教育」
PART 3 連携・協働の視点2 場づくり -会議にはない可能性-
東山田中学校コミュニティハウス設立の経緯
「箱」ができた後は、「魂」を入れることが大切
評価から離れた「場」の重要性
カリキュラムづくりにも地域が関わる時代
人が集まり、情報が行き交うプラットホーム
PART 4 連携・協働の視点3 防災 -学校と地域をつなぐツール-
3千人近くが集う学校・地域合同の防災訓練
防災訓練を通じて、学校・地域の相互理解が深まる
「防災訓練」は、訓練のためだけにやるのではない
「防災」を基点に、学校・家庭・地域の役割を見直す
コロナ禍で見えてきた学校の課題
非常時こそ、学校は地域を頼るべき
コロナ禍におけるポジティブな変化
学校運営協議会をスクラップ装置に
PART 5 連携・協働の視点4 マネジメント -地域と学校をつなぎ成果を出すために-
「地域とともにある学校づくり」には、経営資源が必要
「経営者」としての校長をどう育成し、支援するか
教職員が、主体的・自律的に動くための組織づくり
子どもたちを自律させるための「主権者教育」
PART 6 提言とまとめ-私たちはこれからも歩み続ける-
「誰一人取り残さない」教育を目指す
子どもを「信じる」社会総がかりの教育
私たちはこれからも歩み続ける ―今後取り組んでいきたいこと―
エピローグ これからも共にしなやかに切り拓いていく
関連記事
-
2023.10.04
- 2023年10月 重版情報
学事出版オンライン
ストアで購入
ストアで購入
ネット書店で購入