この連載について
全事研の役員となって事務職員の育成や成長ということを考える中で、学ぶことの重要性を強く認識しているところです。もちろん、体系的な研修制度も資質・能力を身に付ける上で大事ですが、まずは事務職員自身が主体的に学び、学んだことを生かして試行錯誤を繰り返していくことが必要だと感じています。「子どもの豊かな学びのためにも、事務職員として学び続けていきたい」。そんな思いで、私自身の経験から“学び”について考えたことを綴っていきます。
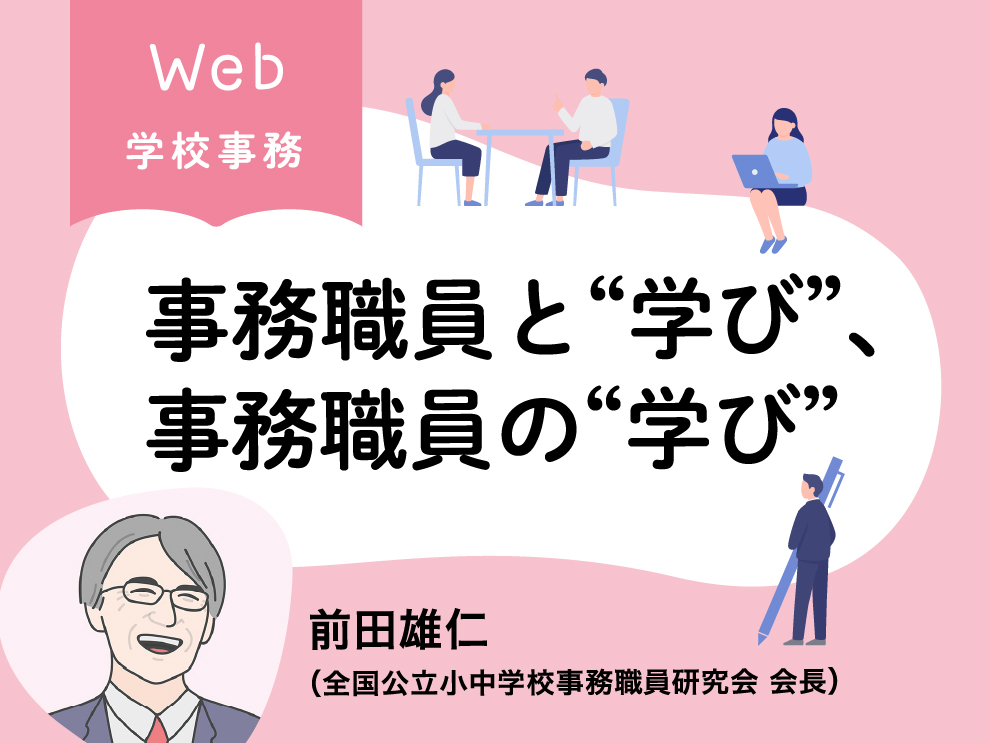
今夏、釜山市(韓国)への教育事情視察に同行させていただきました。釜山市の教育支援庁や、小学校(3校)、釜山博物館、教育博物館などを訪問して、新たな知見を得るとともに、韓国の教育現場の様子を感じることができました。
韓国では、学校は3月に始まり、2月に学年末を迎えます。そして、7月から8月にかけて夏休みがあります。ちょうど訪問時は夏休みに当たり、残念ながら小学生の姿や様子は見ることができませんでしたが、併設されている幼稚園の園児がお迎えを待っているところを少しだけ見させていただきました。
最初に訪問した学校で、夏休みを利用して校舎修繕を行うという話を聞きましたが、訪問した他の2校でも大規模な修繕が行われていました。
教室に入ると、まず大きな電子黒板が目に入り、その左右にはホワイトボードが設置されています。さらにモニターも天井から設置されていました。教室の広さは日本と同じくらいですが、見せてもらった教室に設置された机と椅子は24組だけでした(釜山市のクラス定員の上限は25人らしい)。また、教室によっては、後ろの方で、休憩したり談笑したりできるスペースがあるものもありました。そして、教員の机がとても大きく、そこにはコンピュータはもちろんですが、それとともに電話も置かれ、背後のスペースも含めて十分な教員の執務環境が確保されていました。
空間的ゆとりを感じた教室とは反対に、職員室はとても狭いものでした。職員室には、教頭と、教務主任や支援員(どちらも正式名称ではなく、似たような職)などの職員の机と、センターテーブルがあるだけです。多くの教員は、たまにしか職員室には来ないようで、何日も顔を合わせない教員もいるとのことでした。
職員室で気付いたのは、紙がほとんどないことと、全てのコンピュータが2画面である(教室の教員用も、事務室も)ことでした。明らかに業務がデジタル化されていることがうかがえます。校務支援システムも一部を見せていただきましたが、文書の配信も、業務の決裁過程もとても分かり易いものでした。そして、驚いたことに、このシステムは全国で統一されたものであるとともに、導入されてからなんと20年くらい経っているということでした。
私が勤務する自治体でも校務支援システムがコロナ禍以降に導入されています。しかし、釜山で見てきたものと比べると脆弱にも思えます。私自身が教職員を代表した選定委員にもなっていましたので、多くの機能の追加を要求したのですが、その価格はとても高いもので、強く推すことはできませんでした。
「次世代校務DXガイドブック ―都道府県域内全体で取組を進めるために―」が令和7年3月に文部科学省初等中等教育局学校デジタル化プロジェクトチームから発出されています。次世代校務DXとは、クラウド上での校務実施を前提とし、ロケーションフリーやデータ利活用・データ連携を通じた新しい校務の在り方を指すものです。そして、このガイドブックは教育委員会等に向けて、次世代校務DXを推進するための必要事項がまとめられたものです。
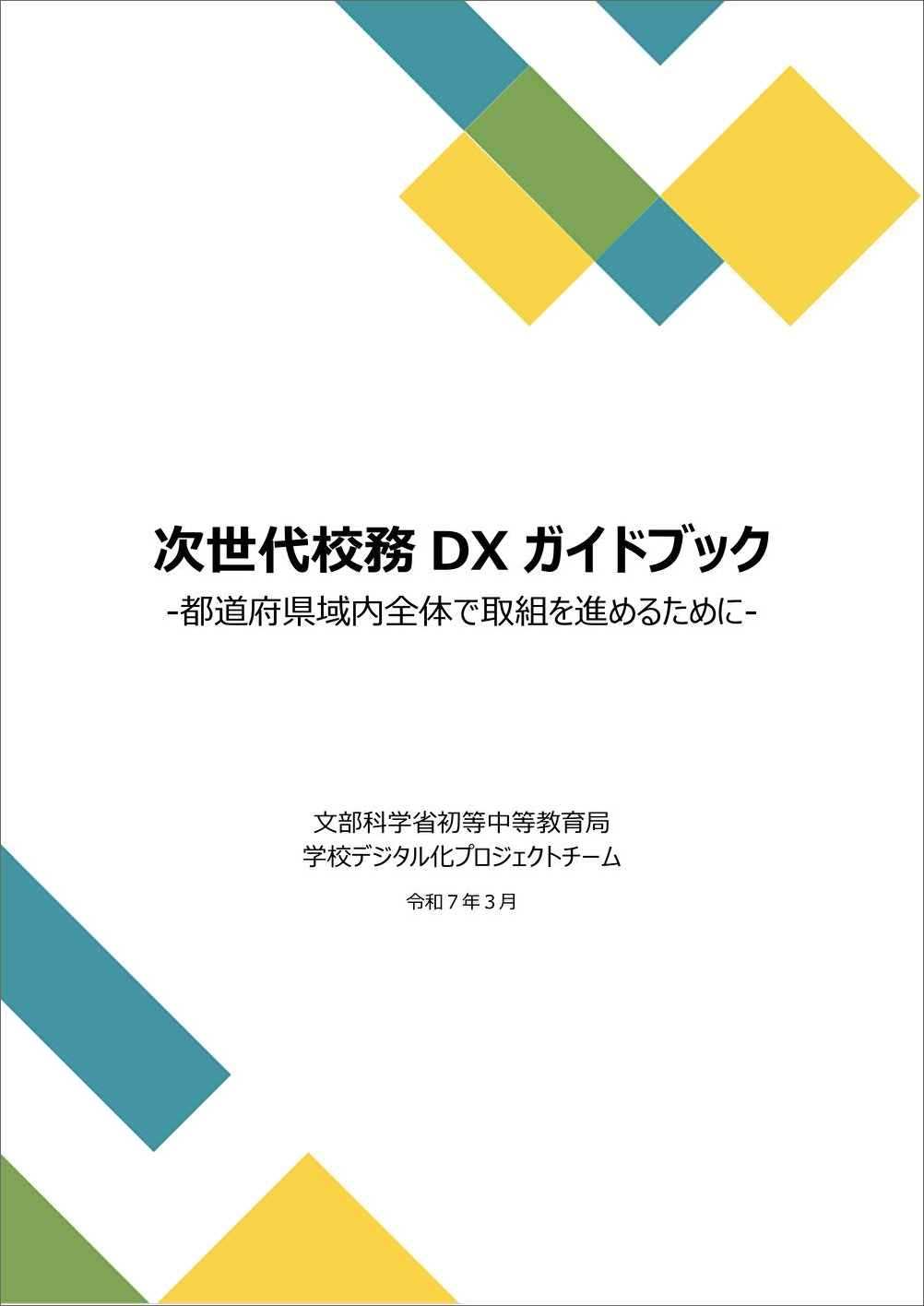
次世代校務DXにより、「学校における働き方改革」「教育活動の高度化」「教育現場のレジリエンス確保」が促進されるものとしています。これまでの校務を単にデジタルに置き換えるだけではむしろ業務を増やすことにつながりかねないことから、まずは3つの主目的に照らして、不必要な業務の見直しや、業務フローの見直し、帳票の必要性やその内容の見直し等、従来から行っている業務の見直しを行い、より最適な業務の在り方を見据えることが必要とされています。
もう少し3つの主目的について、それぞれの観点からお話します。
学校における働き方改革の観点では、校務のロケーションフリー(場所や時間を選ばない)化や、紙ベースの業務からの脱却が挙げられています。まさに私が釜山で見てきた様子と合致するものです。
教育活動の高度化の観点では、学校における日々の学習活動を充実させるための基盤として、各学校や教育委員会に蓄積された様々な校務系情報や学習系情報を円滑に接続させることが挙げられています。
教育現場のレジリエンス確保の観点では、大規模災害発生時や感染症流行時等の非常時のレジリエンス(困難な状況やストレスに直面した際に、それを乗り越えて回復する能力)を高めるためにも、クラウド環境の整備が重要であるとしています。
これらが実現されることに大いに期待するところではありますが、自治体規模等によっては容易でないことも想定されます。改めて、韓国の国単位で統一された校務支援システムの優位性を感じるところです。
もちろん事務室にもお邪魔させていただきました。事務室には事務長の他に2~3名の事務職員が配置されていました。職員室と同様に紙はほとんど見かけずに、2画面のコンピュータが目立ち、校務DXが確立されていることがうかがえました。なお、日本の事務室なら当然にありそうな消耗品も置かれていませんでした。聞くと、教材消耗品などは直接、教室に納品されるとのことでした。
日本で話題の学校徴収金についても聞いてみました。まず、給食費は数年前より無償化されているとのことでした。また、釜山市では教材費や体育着などについてもほとんどが無償のようで、修学旅行費の一部以外では保護者負担はないようでした。その代わりに、放課後学校の授業料の徴収があるそうです。放課後学校とは、学校内で放課後に提供される有料の教育プログラムです。内容は英語や算数から、プログラミングや楽器、スポーツなど、学校ごとに違うそうです。これは教員ではなく、外部講師が担当するもので、この経費の徴収は事務室で行っているとのことでした。
『見たい、知りたい世界の学校』*1によると、韓国の小学校は14:30頃には下校となります。その後、子どもは各自で習い事や塾に通ったり、先述の放課後学校で学んだりするようです。放課後学校も有償ではありますが、民間で行われるものよりもとても安価だそうです。
公立の小学校がそのようなプログラムを提供する意図や由来まで理解することはできませんでした。しかし、どのようなことを学ぶか(あるいは学ばないか)を子どもや親が選択できる幅が日本よりも広いことは良いことのように思えました。
なお、校務DXが確立されていればこそ、事務室が外部講師の雇用などの多様な業務を担っていくことが可能になるものとも思いました。
海外の教育事情視察など容易にできるものではありません。海外を知ることで、日本の教育への新たな気付きもたくさんあったところです。貴重な機会をいただき、大変に有益な経験をさせていただきました。
なお、私の拙いコミュニケーションで聞いた話ですので、実際と異なることがあるかもしれませんがご容赦ください。

前田先生からコメント
事務職員の標準的な職務にも示された学校教育におけるICTについて、事務職員の視点から捉えた書籍『教育ICTがよくわかる本』の発行に携わらせていただきました。それぞれに現場で実践されている事務職員の素晴らしい取組も載っています。学校の現状や、取組の背景、うまくいったこと、うまくいかなかったこと、取組を通して実践者が学んだことなど、読み手にとって考えを広げてくれる本であると強く感じています。事務職員のみなさんの学びのきっかけとなること、そして、事務職員以外の方々には、事務職員との協働や、事務職員の活用を促進していただくきっかけとなることを期待しています。