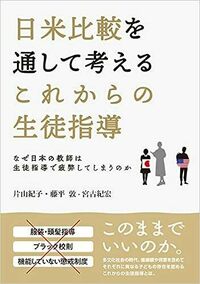この連載について
この連載では、広く、学校で働く教職員、保護者、地域の皆様に向けて、2022年12月に改訂された『生徒指導提要』や、国の施策、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターで行っている調査研究などをもとに、生徒指導の基礎・基本をご紹介していきます。特に、2025年1月からは、いじめや不登校などの生徒指導上の諸課題をテーマに連載をします。
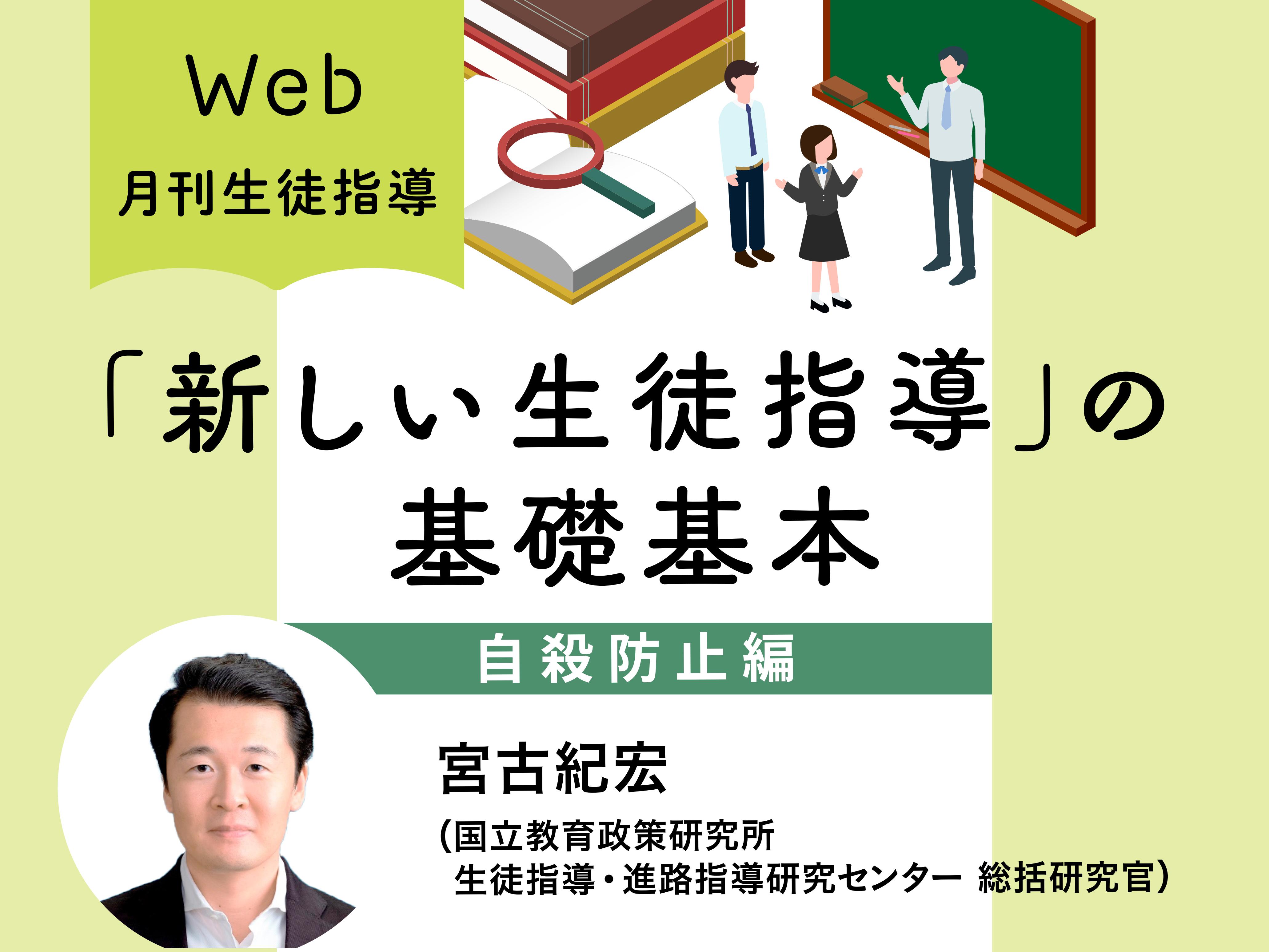
この連載について
この連載では、広く、学校で働く教職員、保護者、地域の皆様に向けて、2022年12月に改訂された『生徒指導提要』や、国の施策、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターで行っている調査研究などをもとに、生徒指導の基礎・基本をご紹介していきます。特に、2025年1月からは、いじめや不登校などの生徒指導上の諸課題をテーマに連載をします。
前回は、小中高生の自殺者数が増加傾向にあることや学校に求められる自殺予防の取組について取り上げました。今回は、海外の研究に目を向け、「学校とのつながり」(school connectedness)と自殺予防を含む健康行動に対する影響について述べます。
本連載の第5回でも国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター(2024)の研究として、中学生の「学校とのつながり」が高いことが、いじめの加害の抑止に関連することを取り上げました*1。
また、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターでは、2024年度から新たなプロジェクト研究「不登校・いじめ等の生徒指導上の諸課題と学校風土等との関連及び効果的な取組等に関する調査研究-地域との中・長期的な連携を生かして-」をスタートさせ、大規模な学校風土研究に着手しています。その2024年度調査の結果については、同センターが主催している「令和7年度生徒指導研究推進協議会」にて研究報告をしています。同協議会については、以下のYouTubeの文部科学省のチャンネルからご覧いただけます。
上記の同協議会では、日本の中学生の「学校とのつながり」を高めることが、いじめの加害の抑止だけでなく、欠席をしたいという思い(欠席意向)や実際の欠席(欠席行動)の抑止、社会的態度・行動(特に「思いやりと責任ある行動」や「学習意欲」、「共感性」、「課題解決力」、「活力」)の育成に関連することが報告されています。
このように、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターでは「学校とのつながり」に着目した学校風土研究を進めていますが、「学校とのつながり」の研究は、決して新しいものではありません。
アメリカでは、1994-95年に中学生や高校生であった生徒を対象に、その集団を現在も継続して追跡しているAdd Health(National Longitudinal Study of Adolescent Health)という縦断調査があります*2。。このAdd Healthで得られたデータは、広くデータシェアリングされており、多くの研究者によって、様々な再分析が行われています。その中でも、特に、レズニックたちの研究は、Add Healthのデータを用いて、「学校とのつながり」が、青少年の飲酒や喫煙、薬物乱用、性的行動といった健康行動へのリスクの未然防止に最も重要な役割を果たすことを明らかにした研究として有名です(Resnick et al., 1997)*3。
「学校とのつながり」の定義は、研究者によって異なりますが、2004年のウィングスプレッド宣言の定義を踏まえて、米国疾病予防管理センター(Centers for Disease Control and Prevention: CDC)が示した、「子どもが、学校にいる大人や他の子どもが、自分の学習だけでなく、人として自分という存在そのものを気にかけてくれているといった実感のこと」は、広く受け入れられている定義の一つといえるでしょう*4。
近年の「学校とのつながり」の研究では、健康行動に関連する一次研究を広くレビューし、統合するといったメタ分析の手法を用いるものも登場しています。それにより、より質の高いエビデンスが算出されています。また、CDCも1990年代から実施してきた「青少年リスク行動調査」に、2021年の調査から「学校とのつながり」の質問項目を導入しています*5。これら「学校とのつながり」の研究動向については、筆者が別稿にて行っていますので関心のある方はそちらをお読みいただけたらと思います *6。
これらのメタ分析の研究から、例えば、一般のグループとハイリスクのグループ、性的マイノリティのグループのいずれにおいても「学校とのつながり」が高いほど、自殺念慮や自殺行動が抑止されることを明らかにした研究(Marraccini & Brier, 2017)*7 や、「学校とのつながり」が、メンタルヘルスや薬物使用、暴力といった健康領域に保護的に機能することを明らかにした研究(Rose et al., 2024)*8などがあります。
上記を始めとした、海外の「学校とのつながり」の先行研究の蓄積を通して見えてくることは、「学校とのつながり」が、子どもの現在だけでなく、自殺予防をはじめとする将来の健康行動全般(例、飲酒や喫煙、薬物といった依存行動、性的なリスク行動、暴力等)に影響を与えるという頑健なエビデンスです。
学校は、学齢期の子ども全てを包括する重要なシステムです。その利点を捉えて、学校を基盤に「学校とのつながり」の育成を柱とする政策論や実践、すなわち、発達支持的生徒指導の推進を構想していくことは、子どもの自殺予防を含む心身の健康の増進を図る上で、最重要事項の一つといえるでしょう。